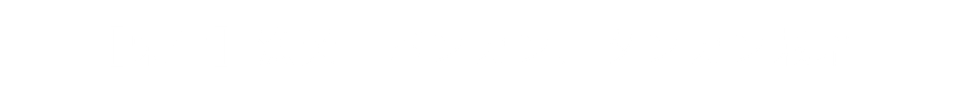公共施設など
概要
漁業
・江戸期から大正初期までカツオ漁の基地として栄え、全国に知られた鰹節産地だった。
・1822(文政5)年の江戸の全国鰹節番付では「役島節」の名で大関、明治時代には全国水産博覧会で上位入賞が記録されている。
・明治30年代にカツオ漁は衰退したが、トビウオ漁が昭和30年代まで続き、一時は100艘ものトビウオ船があった。
・1964(昭和39)年の栗生港着工、1978(昭和54)年の栗生漁港着工と整備が進み、現在も10隻程の専業漁船を含めて30隻が栗生港を拠点 にしている。
・港には屋久島漁協出張所があり、製氷や冷蔵、冷凍能力がある。
・黒潮本流が東シナ海から太平洋に抜ける栗生の海は漁種が多く、季節を越えてさまざまな漁がおこなわれている。
・殆どが一本釣りで、大きい船は屋久島南部沖からトカラ列島方面まで出漁し、小型の船は沿岸で操業している。
・大型のイシアラ、アカバラ(カンパチ)、タルメ(メダイ)などの 高級魚が多いのが特徴だが、ハガツオも対象になっている。
・一本釣りではないが、初夏には養殖ブリの稚魚としてモジャコ漁も行われている。
ポンカン、タンカン栽培
・1926(大正15)年頃、屋久島にポンカンを導入した黒葛原兼成氏から栗生の岡留重作氏が苗をもらい受けて周囲にも分けたのが、ポンカン栽培の始まりといわれている。
・本格的なポンカン栽培は戦後のことだが、その後1970(昭和45)年 頃導入されたタンカンが主力作になっている。
・栗生の柑橘類は雨量が少なく、日照量が多いので甘みが強いといわれている。
【資料】
1 屋久町郷土誌第1巻村落誌上
2 区長他聞き取り
写真
タルメ水揚げ
栗生の西、十島の北付近で捕れるタルメが水揚げされる。 |
タルメ
タルメは高級魚として人気がある。 |
タルメ漁協箱
タルメは殆どが本土に出荷される。 |
アカバラ水揚げ
一本釣りではアカバラ(カンパチ)の水揚げも多い。 |
アカバラ
アカバラ。 |
イシアラ水揚げ
大型が多いイシアラの水揚げ。 |
イシアラ
イシアラ。 |
イシアラ計量
40kgもあるイシアラの計量。 |
ハガツオ
沿岸ではハガツオが釣られる。 |
ポンカン
ポンカン。 |
ポンカン採取
ポンカン採取、後ろの山は七五岳。 |
ポンカン収穫
ポンカン収穫作業。 |
収穫ポンカン
収穫されたポンカン。 |
タンカン
タンカン。 |
タンカン収穫
甲ヶ峰が見えるタンカン園。 |
タンカン採取a
タンカンの採取。 |
タンカン採取b
タンカンの採取。 |
収穫タンカン
収穫されたタンカン。 |