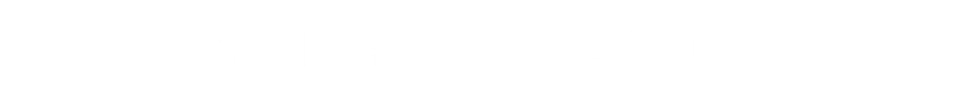栗生神社・満丸神社
概要
栗生神社
・祭神は益救神社と同じ彦火火出見尊(ヒコホホデノミコト)であるが、由緒来歴の詳細は定かではない。
・1908(明治41)年明細帳によれば、村社である栗生神社は益救神社に次ぐ創建とされており、藩政期にも新嘗祭等には益救神社から出務したとされる。
・また、栗生岳山頂を栗生神社の奥の院と称したとされている。
・社殿内の小国神社は中山神社と花尾神社の合祀で、丹後の局や源頼朝を祀るとされているが来歴は定かではない。
・今も村の守り神として浜下りや十五夜綱引きなど伝統行事の拠点になっている。
・初詣をはじめ折に触れての宮参りの対象として、地域住民のよりどころになっている。
・境内のクリオザサは屋久島、種子島に固有のイネ科植物で町指定天然記念物だが、シカの食害が激しい。
・満丸神社と浜神様(稚御魂神社)、蛭子神社(恵比須様)は、栗生神社の境外摂社とされる。
・例大祭は春秋2度、春には浜下り行事がおこなわれる。
栗生神社例大祭 (平成29年11月22日秋大祭記録)
・栗生神社の例大祭は春秋2回行われるが、秋は新嘗祭に近い11月22日におこなわれた。 *春の例大祭は伝統行事「浜下り」の項で紹介。
・前日21日、集落役員や有志が境内を清掃し、しめ縄をつくって準備を行った。
・22日当日は、新嘗祭などには益救神社から出務があったという藩政期からの伝統に従って、益救神社宮司を斎主として神事を執り行った。
満丸神社 (資料135)
・集落東側山腹のシイの巨木を交える森林にある。
・明治時代に栗生神社に合祀されたが、その後分離したらしく現在地にある。
・ご神体の自然石があり、平清盛の妻であった二位尼を祀るとされるが来歴は定かでない。
【資料】
1 屋久町郷土誌第1巻 村落誌上
2 屋久島、もっと知りたい ~人と暮らし編~ 下野敏見
3 岩川明氏資料および聞取り
4 屋久島町文化財資料 教育委員会
5 区長他聞き取り
写真
栗生神社正面全景
栗生神社は集落の北端、山に通じる道のわきに鎮座している。 |
栗生神社社殿
栗生神社社殿 |
社殿内本殿
栗生神社本殿は社殿(拝殿)内に置かれている。 |
社殿内小国神社
社殿内には、中山神社と花尾神社を合祀した小国神社の本殿も置かれている。 |
秋大祭しめ縄つくり1
先端の鬼の絵。 |
しめ縄つくり2
しめ縄つくり2 |
しめ縄飾り付け
祭礼のぼりが立てられ、ま新しいしめ縄が鳥居を飾る。 |
秋大祭清掃準備
境内も清掃されて大祭の準備が整う。 |
秋大祭神社全景
22日秋大祭当日の栗生神社 |
秋大祭社殿
のぼりが並ぶ社殿(拝殿)への参道。 |
秋大祭社殿内
集落役員、有志がそろって大祭の神事が始まる。 |
秋大祭開扉
例大祭では、本殿の扉が開かれる。 |
開かれた本殿
開かれた本殿 |
益救神社宮司祝詞奉上
江戸時代以来の伝統に従って斎主を勤める益救神社宮司が祝詞奏上。 |
参会者拝礼
区長以下、参会者一同拝礼。 |
クリオザサ標柱
屋久島、種子島固有のイネ科植物クリオザサの町指定天然記念物標柱 |
クリオザサのアップ
クリオザサのアップ |
満丸神社
集落東側の山腹森林内にある満丸神社は栗生神社の境外とされている。 |
満丸神社内部
平清盛の妻、二位尼を祀ると伝えられる満丸神社内 部、丸い自然石がご神体といわれている。 |