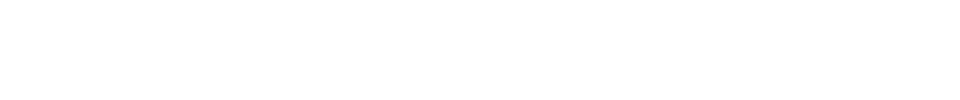正月7日行事(鬼火焚き・祝い申そう)
概要
鬼火焚き史料
・悪霊を焼き払う行事として「どんど焼き」などと呼ばれる全国的行事だが、屋久島はその南限にあたる。
・屋久島では正月行事として、1月7日に全集落で行われる。
・栗生では明治初めまで、集落内江川で行われていたというから、藩政期からの伝統である。
・栗生では「どんどや」という各地の呼称に近い名もある。
・明治時代に鬼火焚きが途絶えた時期があったが、鬼子が生まれたのでたたりとされ、復活させたという言い伝えがある。
平成30年1月7日記録
・8:00に集落役員や消防団、青年たちが作業開始、枝を一部残した松を浜に立てて、それに先端の葉を残した孟宗竹を添わせる。
・周囲にハマガシ(ウバメガシ)、笹をカズラで括ってひとかかえ以上の太さにして、先端に鬼の絵を吊るした。
・住民が持ち寄った正月飾りも積みあげ、当日は雨が予想されたので 例年より早く14:00に点火された。
・火の盛りが過ぎたところで倒し、先端と鬼の絵を伐ってこれも燃やした。
・ほぼ燃え尽きたところで、ウバメガシを縁起物として持ち帰る人々も多い。
祝い申そう
・村々を巡る祭文語りの門祝いが定着したと言われており、大隅半島南部と種子島、屋久島、硫黄島に伝えられている。
・もとは「福祭文」だが、屋久島では「くさいもん」とか「祝い申そう」と呼んでいる。
*以下、平成30年1月7日記録
・小中高校生と指導役の青年たちが、雨模様で例年より1時間半早く16:00栗生神社に 集合、祝い申そうを7回歌って3班に分かれて出発した。
・喪中を除く各戸を訪ね、祝い申そうを歌ってまわった。
・昔は家々でご馳走が出され、青年には酒もふるまわれたが、今はお菓子やお祝いが渡される。
・祝い申そうの唄<祝い申そう、祝い申そう、いつもよな今年は、恒 例の門松 栄えて候よ 栄えたる枝に うぐいすがとまって さえず るように うちの亭主 これの宿を 見渡し見れば 西方の隅々の 泉酒のわき候 黄金のびんに 白金の ひしゃく くんでも くんでも尽きません 祝うてヤホホノホー 祝うてヤホホノホー >
【資料】
1 屋久町郷土誌第1巻村落誌
2 屋久島、もっと知りたい~人と暮らし編~ 下野敏見 3 区長他聞取り
写真
前日の神社清掃
朝から栗生浜に集落役員や消防団、青年たちが集り、 鬼火焚きの準備が始まる。 |
浜の御旅準備
砂浜に、一部の枝を残した松を重機で立てる。 |
鎧武者着付け
燃えると音を立てるバチバチノキ(ウバメガシ)は鬼火 焚きに欠かせぬ材料。 |
鎧武者が控える社殿
カズラを叩いて柔らかくし、くくり縄にする。 |
一同拝殿へ
先端の鬼の絵。 |
大祭神事宮司
周囲に笹やバチバチノキを添え、午前中には栗生浜に出来上がった鬼火。 |
大祭区長
火をつける頃には七草の子供もやってきた。 |
ご神体取出し御幸祭
ポンカンも配布された。 |
ご神体神輿へ
多数の住民が、厄払いの新年行事に参集した。 |
ご神体神輿搬出
燃え盛る鬼火焚き。 |
出発前武者神輿
燃えあがった後、最後は倒して鬼も燃やした。 |
子供神輿
最後の火でスルメをあぶる人もいたほか、ぜんざいのふるまいもあった。 |
出発前太鼓
祝い申そうの子供たちと指導役の青年たちが栗生神社に集合、祝い申そうを7回歌って出発した。 |
浜下り行列
3グループに分かれて集落を巡った。 |
行列の子供神輿
各家庭の玄関前で祝い申そうを歌う。 |
ご神体の神輿
喪中を除く全戸をまわる。 |