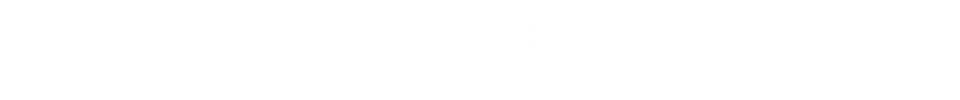正月7日行事(鬼火焚き・祝い申そう)
概要
鬼火焚き(オントビー) (資料1、2、3)
・悪霊を焼き払う行事として「どんど焼き」などと呼ばれる全国的行 事だが、屋久島はその南限にあたる。
・屋久島では正月行事として、1月7日に全集落で行われる。
・オントビーといわれることも多い。
・湯泊の鬼火焚きで先端に掲げられる鬼の絵は、金棒を持った裸の男鬼で急所をムカデに噛まれており、痛いところを噛ませて悪魔を追い出すと言い伝えられている。
平成30年1月7日記録
・朝のうちに集落役員や消防団、青年たちが生活館に集合し、材料採取に出かけた。
・この日は七草なので、鬼火焚きで点火の役を果たす七草の子供は神社にお参りをした。
・材料をそろえて湯泊の浜に、先端が二股になった木を立てる作業から準備が始まった。
・雨予報で時間を繰り上げて作業が進み、13:00前には先端に掲げる鬼の絵にお神酒をあげ、鬼火焚きの孟宗竹が二股の木に添わせて立ち 上げられた。
・孟宗竹の周囲に笹やバチバチノキ(ウバメガシ)が束ねられ、七草の子供が火を入れた。
・燃えあがったところで鬼に浜の石を投げつけて鬼の絵をボロボロにした。
・家から持参したお供え餅を青竹に挟んで焼くが、これは縁起物として家で食べるという。
・最後に孟宗竹を倒し、燃え残ったバチバチノキを持ち帰り、家の火で炙ってバチバチと音を立てさせる。
祝い申そう (資料123)
・昔の祭文語りの門祝いが定着したと言われており、大隅半島南部と種子島、屋久島、硫黄島に伝えられている。
・もとは「福祭文」だが、屋久島では「祝い申そう」とか「くさいもん」と呼んでいる。
・湯泊でも、以前は青年たちの行事だったが、今は子供たちが行っている。
・湯泊の「祝い申そう」歌詞は、屋久町屋久町郷土誌第1巻村落誌に掲載あり。
平成30年1月7日記録
・雨模様なので例年より早く、子供たちが15:30生活館を出発して集落の家々を廻った。
・門祝いとして、各戸の玄関先で声をそろえて「祝い申そう」を歌う。
・以前は、お神酒とお膳のふるまいもあったが、今は子供たちなので お菓子が渡された。
【資料】
1 屋久町郷土誌第1巻村落誌
2 屋久島、もっと知りたい~人と暮らし編~ 下野敏見 3 区長他聞取り
写真
湯泊神社へ七草
七草祝いの日なので、鬼火焚きの点火役でもある七草 の子供が湯泊神社へ。 |
神社七草参詣
湯泊神社で七草参り。 |
鬼火柱立て
海岸の岩を足場に二股の木を立てる。 |
鬼の絵に祈願
鬼の絵にお神酒をあげて、区長らが悪魔祓いを祈願。 |
鬼火孟宗立て
二股の柱を支えに、鬼の絵を吊るした鬼火焚きの孟宗 竹を立てる。 |
先端の鬼の絵
先端の鬼の絵。 |
鬼火完成
鬼火が立ち上る頃は、住民も参集する。 |
鬼火火入れ
七草の子供による鬼火焚きの火入れ。 |
鬼火燃え上がる
燃えあがる鬼火。 |
燃える鬼火
湯泊の浜で燃える鬼火焚き、石投げが始まる。 |
鬼に石を投げる
鬼の絵に浜の石を投げる。 |
石でボロボロ鬼
投石でボロボロになった鬼。 |
焼くお供え餅
家から持参した正月のお供え餅。 |
お供え鏡餅を焼く
お供え鏡餅を焼いて持ち帰り、縁起物として食べる。 |
鬼火を倒す
鬼火を倒す。 |
笹やバチバチを取る
)最後にバチバチノキを取り、家に持ち帰って火で炙り、 厄払いに音をさせる。 |
祝い申そう集落廻り
祝い申そうの子供たちが集落を廻る。 |
家を訪ねる1
家を訪ねる1 |
家を訪ねる2
家を訪ねる2 |