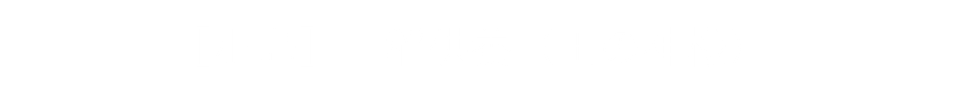稲供養(田の神様)
概要
・水田耕作をしている人たちの田の神様の祭り(旧暦9月19日)だが、明治末の導水事業の成果に感謝して水路を意味する井手供養の名もある。
・稲作農家の当番が田の神様に参拝した後、導水事業に功績のあった岩川若松氏の頌徳碑前で区民に持ち寄りの米を炊いた “にんこ(握り飯)”を振舞う。
・かつては、秋の稲刈りの後の行事で新米の “ にんこ ” の振舞いだったと思われるが、超早場米で夏収穫になった今も秋に行われている。
*以下は平成30年10月27日の記録
・10:00に稲作農家の当番が公民館に集合し、奥さん達は握り飯つくりに取りかかった。
・男性陣は県道上の田の神山に向かい、森と田の神様の石の周囲を清掃した。
・握り飯も出来上がって、12:30頃世話役の、男性陣が田の神 様に小島の米の“にんこ”と魚、榊を供え、線香を立てて参拝した。
・一同は田の神様森で車座となって縁起物のにんことお神酒をいただいた。
・16:00過ぎから小島神社の岩川若松頌徳碑にも、先人の功績に感謝して稲作農家の人たちが参拝した。
・続いて、頌徳碑を訪れる住民には “ にんこ ” が渡されるので、この行事を“にんこもい(にんこもらい)”と呼んでいる。
・広げられたシートの上には “にんこ”と料理が並べられ、住民の皆さんに振舞われた。
・この行事は、屋久島では珍しい稲作基礎の農業集落小島の導水事業と開田の重要性を伝える貴重な伝統行事である。
【資料】
1 屋久町郷土誌第一巻村落誌上
2 区長他、住民多数聞取り
写真
稲供養のにんこ振舞
稲供養のにんこ振舞は小島の成立ちを伝える行事である。 |
奥さん達にんこ作り
稲作農家の奥さん達が公民館調理室でにんこ(握り飯)をつくる。 |
主役のにんこ
大量につくられる主役のにんこ。 |
田の神森
県道上にある田の神森(ヒガイノハーの森)。 |
田の神様にお供え
清掃された田の神様前にお神酒とにんこ、魚、榊を供える。 |
田の神様拝礼
稲作農家の当番が田の神様に拝礼する。 |
にんこ他をいただく
一同は田の神森でにんこと魚をいただく。 |
一同頌徳碑に拝礼
小島神社に移動し、そろって頌徳碑に拝礼する。 |
頌徳碑
明治時代の水路開削、開田の功労者岩川若松の頌徳碑。 |
お神酒をいただく
お神酒をいただく。 |
皆にお神酒とにんこ
皆にお神酒とにんこ。 |
にんこ渡す1
訪れる人たちににんこが振舞われる1 |
にんこ渡す2
訪れる人たちににんこが振舞われる2 |
にんこと料理の振舞
訪れる人たちはシートに座ってにんこと料理をいただく。 |