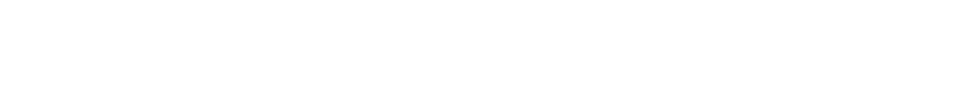芋塚岳岳参り
概要
岳参り (資料12)
・屋久島の岳参りは、山の恵みに感謝する行事として古くからおこなわれてきた。
・岳参りは、世界文化遺産で評価される富士講のように高山を神聖化する信仰登山で、日本中でみられる山岳信仰の形だが、本格的な行事は屋久島が最南といわれる。
・各集落が奥岳や各地域に縁のある前岳に登り、そこに祀られる屋久島の山の神、一品法寿大権現(神道名:彦火火出見尊ヒコホホデ ミノミコト―益救神社や栗生神社などの祭神)にお参りする。
・若者減少などで少なくなったが、伝統文化の見直しなどで復活傾向にある。
小島の岳参り (平成30年9月24日の記録) (資料13)
・小島の岳参りは集落の背後にそびえる芋塚岳794mである。
・旧暦8月15日、つまり十五夜に行うのが小島の特徴である。
・様々な行事と同様に年替わりで担当班が行事を仕切る。
・かつては、山中一泊の宮之浦岳参りと日帰りの芋塚岳参りがおこなわれたが、現在は宮之浦岳には行っていない。
・7:00に使者であるトコロカン役の5名が公民館を出発、7:15に南部林道から芋塚岳登山道に入る。
・ヒルに悩まされながら前岳特有の急斜面を登り、9:30に山頂に到着。
・山頂の祠にお神酒、米、塩、地区民に託されたお賽銭を供えて一同参拝。
・最後に山の榊を手で折り、里への土産として下山した。
・岳参りを送り出した里では、担当班の人たちがトコロカンを迎えるために神社を清掃し、奥さんたちは料理を準備して下山を待った。
・12:00過ぎに小島神社に到着した岳参りの一行は、待ち受ける里の人たちに山の榊を分け、神前にも供えて参拝した。
・神事の後は、待ち受けていた一同とともに迎えの宴となった。
・一連の迎えの行事は明治時代までは「一本松」と呼ばれている場所と伝えられているが、現在は小島神社で行われている。
・岳参りの日は十五夜でもあるので、続いて夕方から綱引き行事が行われた。
【資料】
1 屋久町郷土誌第一巻集落誌上
2 屋久島、もっと知りたい~人と暮らし編~ 下野俊見 3 区長他住民聞き取り
写真
集落と岳参りの芋塚岳
小島のシンボル芋塚岳794mが岳参りの山である。 |
芋塚岳山頂794m
大きな花崗岩の露頭の上が芋塚岳山頂である。 |
南部林道から入山
使者役のトコロカン5名は集落上の南部林道から登山道に入る。 |
登山道急斜面登攀
前岳特有の急斜面を直登する登山道は、近年ヒルも多くつらい登りである。 |
山頂近い見晴し
山頂近くでは、苦しい森の登攀を抜けて見晴らしがよくなる。 |
小島中心付近景観
山頂手前で山の瀬に続く海岸と小島の中央部がよく見える。 |
芋塚岳山頂の祠
祀られている神様は定かではないが、山頂には祠がある。 |
山頂祠に供え物
山頂の祠には、お神酒とともに持参した米や塩、託されたお賽銭を供えた。 |
一同祠に拝礼
一同祠に拝礼。 |
持ち帰る榊を採る
山上から里に持ち帰る榊を採る。 |
小島神社で迎えの準備
小島神社では岳参りの下山に備えて、清掃など準備がおこなわれる。 |
奥さん達は料理
担当班の奥さん達は、公民館で料理の準備をする。 |
神社拝殿迎えの席
下山前には、小島神社拝殿に迎えの席が整えられる。 |
山の榊を持って下山
12:00過ぎに下山した岳参りの一行は、山の榊を持って小島神社に到着した。 |
人々に榊を分ける
迎えに来ている集落の人たちに榊を分けた。 |
神前に榊を供える
持ち帰った山の榊を神前に供える。 |
一同神前に拝礼
一同神前に拝礼。 |
迎えの宴1
神事の後、迎えの宴となる1。 |
迎えの宴1
迎えの宴2。 |