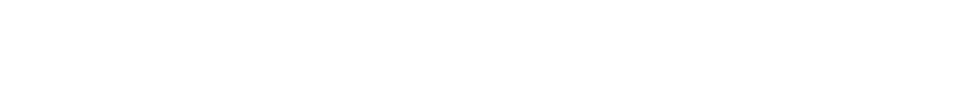自然
概要
尾之間の代表的な「自然」に関して紹介する。
モッチョム岳
尾之間集落を見下ろす象徴的な、花崗岩の岸壁を持つ山。標高940m(国土地理院)。女性性器を示す方言名が名の由来とよく言われるが比較的近代になって言われ始めた風説のようだ。本富岳と表される。耳岳・割石(わりし)岳と並んで「尾之間三山」とされ、縦走路も存在した。但し尾之間集落からモッチョム岳に登る登山道同様現在は失われており、尾之間三山全部の頂上付近に祠は存在しているものの2017年現在の岳参りの対象からは外れている。
蛇之口の滝(ハイキングコース)
尾之間温泉の裏手を起点に、かつてのサトウキビ畑の跡を辿り 元々あった鈴川沿いを遡上してゆく古い歴史のある登山道(尾之間歩 道)をなぞるようにつなぎ、途中分岐し蛇之口の滝へと至る1983年に環境省が整備したハイキングコース。
但しその後崖崩れ等の度に迂回路・別道が作られ「ハイキングコー ス」という名称には多くの人が疑問を覚える状態になっている。
途中炭焼き窯や畑の石垣等の暮らしの痕跡、そして時期により希少植物も含む屋久島低地の植生を観察・楽しむことができる貴重な場所ともなっている。
ミヤカタノウラ(鑑真上陸地)
中国律宗の指導的僧侶、戒律僧であった鑑真(688-763)は、朝廷の意により第9次遣唐使団で招聘された。困難を伴い五度失敗、失明ののち6度目に753年の第十次遣唐使帰路第2船に乗組み日本へ渡る。屋久島には12月12日に寄港した記録があり、それがこのミヤカタノウラだという伝承がある。