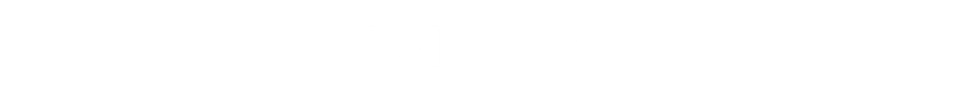二十三夜
概要
・夕刻より翌朝まで 日の入り、月の出、日の出を拝む、年間を通して最も長い集落行事。
・月の出が一年を通したなかでも最も遅く、特に正月明けの二十三夜が最も闇夜が続く事から月を崇める風習が生まれたと考えられる。二十三夜様とは月の事。
【場所】 原公民館
【平成31年1月28日 事次第】
・17:00時集合。
・その時点で料理等は準備されている。
・日の入りの時間は17:48とのこと。それに合わせて祭壇を準備する。
・時間前に区長挨拶等も挟む。もとは出郷者・漁師・出征兵士等の安全を祈願する行事であった旨の説明あり。
・代表の十人組の内、不幸等無かった人の中から「神様役」二人「ござ持ち役」一人が決められ、それぞれ正装。神様は催しの最中一言も口をきいてはいけないとされる。
・かつてはお寺のお坊さんがお経をあげたと言うが、現在は無くなっている。
・供え物は郷土史にも記載された決まりがあり。具体的に・月形の大白餅(月なり)・丸い大赤餅(日なり)・手ごろな 大きさの紅白餅1 2個づつ・小さな白餅を3 6 5個・尾頭付きの魚二匹・セ(カメノテ)12個・かんづけ12切れ・トコロの根の輪切り12切れ・お神 酒はかんびん二本に笹をつけ、他の二本におせん米の白スズの計四本・ 米塩一皿づつ・海水に笹をつける。
・二礼二拍手一礼
・日の入りの後月の出の深夜まで、食事のあとただひたすら待つ。かつてはカラオケ等もしたらしいがこの日はテレビでサッカーのワールドカ ップがあった模様。
・12時半ごろ、月を拝む。祭壇を片付け一旦解散。
・日の出は7時13分。再度集合、お参りし、おもち等を分け合い解散。
【参考文献】 屋久町郷土史第二巻 P192