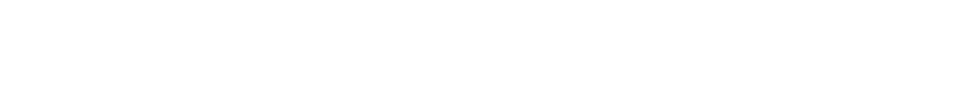船行神社・船行本要寺
概要
<船行神社> (資料1、2)
・船行集落の山手奥にある。
・祭神は大山祗命(おおやまずみのみこと)、益救皇大神(やくのす めらがみ)。大山祗命は山の神として営林署でも祭られている神である。
・本殿に祭ってあるご神体は円筒形の石で、白い布で覆われている。 本殿は3つに仕切られており、円筒形の石のご神体の両側にも別のご神体を祭ってある。本殿の前に鳥居が三本あり、その上に掛けられている絵三枚もそれぞれ異なっている。手前は白塗りの上に赤の十字、その奥は白く塗られた茄子三本、その奥は白馬の彫刻がある。ご神体のところにも三本の茄子を彫り込んだものが三枚ある。馬の絵は、昭和12年1月に本殿を改築した時に馬の夢を見るという神のお告げがあり、当時の粟穂小学校の先生に描いてもらったもの。
・昭和12年に境内の杉を伐採して改装した。伐採した杉の年輪が600年経過していたことから、それ以前に氏神として祭られていたと思われる。
・古来より子宝の神として、屋久島全島から妊婦が安産祈願に訪れている。
・旧暦の1月11日に大祭を行うが、左側のご神体では例祭として旧 暦6月0日に、右側のご神体では旧暦8月20日に祭りごとが行われ ている。
・神社の境内では、夏祭り、旧暦8月15日には綱打ち、綱引きが行 われる。
・絵馬箱があり、お賽銭と別に1枚百円を賽銭箱に入れ、願いを書いて絵馬を吊るす。
・境内に生えている杉は「船行大杉」と言い、「屋久島町指定天然記念物」となっている。
<船行本要寺>
(資料1)
・船行神社の奥にある船行公民館の隣にある、法華宗の寺である。
・長享年間(1487~1489年)、屋久島に金剛院日増上人が来島し巡教した際に建てられたが、明治2年の廃仏毀釈により、寺は廃止され、宝物などは焼却された。その後、大正初期に神社隣に建てら れた青年クラブ内に日蓮様を祭るようになり、昭和49年の公民館改修時に現在の場所に新たに寺が建てられた。
・祭壇には位牌が置かれており古いものは大正のものもある。位牌に は法華宗特有の「妙法」の字が法号の上に書かれている。
・厨子は屋久杉で作られている。
【参考文献】
1.屋久町郷土誌 第三巻集落誌 下
2.鹿児島県民具第4号-屋久島特集号-
写真
船行神社外観
大杉が立ち並ぶ船行神社外観。 |
船行神社鳥居
船行神社入口の鳥居。 |
船行神社拝殿外観
船行神社拝殿外観。 |
船行神社境内1
船行神社境内の全景1。船行大杉が立ち並ぶ。 |
船行神社境内2
船行神社境内の全景2。船行大杉が立ち並ぶ。 |
本殿外観正面
船行神社拝殿奥の本殿外観正面。3つの扉があり、左右に白馬の絵が描かれている。 |
本殿外観横から
船行神社拝殿奥の本殿外観横。 |
出産御礼の幟
本殿に彫られた三本の茄子。 |
本殿の茄子の彫刻
本殿左の厨子。 |
本殿中央の厨子
本殿中央の厨子。 |
本殿右の厨子
本殿右の厨子。 |
本殿中央の厨子の茄子の彫刻
本殿中央の厨子に彫られた茄子。 |
|
船行神社拝殿内 
船行神社拝殿内。 |
賽銭箱と絵馬箱 
船行神社拝殿内の賽銭箱と絵馬箱、掛けられた絵馬。 |
十五夜綱打ち 
船行神社境内で行われる十五夜の綱打ち。 |
|
船行本要寺 
船行本要寺外観。 |
船行本要寺拝殿内 
船行本要寺拝殿内。簡素な造り。 |
屋久杉製厨子と位牌 
船行本要寺拝殿内の屋久杉製厨子と位牌。 |