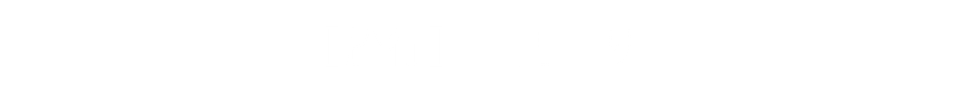門回り
概要
・毎年1月7日、鬼火焚きと同じ日に行われる厄払いの儀式である。
・「門回り」と言ったり「祝い申そう」とも言う。
・主に青年団で構成された1班3人を5班体制で1班10戸ほどを歩いて回る(1班のみ、車)。子供は参加しない。訪ねても寝ている家 や事前に断りがあった家は回らない。
・祝いうたは、神社、公民館・お寺、個人用の3種類がある。個人用 は各家の家長の名前をうたい、「○○ぶり」の部分は都度確認をして 「健康・長寿・大漁(漁師)」のいずれかを入れて唄う。
・船行では節分のような事も門回りの際に行う。
・各家ではバチバチノキ(正式名はケウバメガシ)の小枝、小石3 つ、豆3つを準備して門周りを待っている。
<祝いうた>
(神社)
「いつもよい今年は 光栄の門松 さってもみごとに栄えた 栄えたも同様 四方のすみずみに ゆずみだけが たとた たとたも同様 塩金びんに 黄金(こがね)のこびちゃ くんでも・くんでも・ちきそもうそう えんそ同様 祝うて申す」
(公民館・お寺) 「いつもよい今年は 光栄の門松 さってもみごとに栄えた 栄えたも同様 東の方の枝には うぐいすが とまって 西の方の枝には トビウオが とまって うぐいすの目ぇ~に はえたるイネは ひともとかえせば 一千石 ふたもとかえせば 二千石 その宿み~れば 米の俵が 一千石 もの俵が 二千石 祝うて申す」
(個人)
「いつもよい今年は ○○さんの方こそ
○○ぶりがようして 四方のすみずみに 銭と金 いでこうでそうろう 祝うて申す」
<門回り(祝い申そう)>
(平成30年1月7日)
・午後6時、船行神社に集まり、班分けが書かれた紙と、祝いうたが 書かれた紙が配られる。本殿にロウソクを灯し、皆で拝礼したのち、 直会のお神酒をいただく。豆を各班づつ袋に入れる。船行神社で以下 の3~5の流れを行う。公民館、本要寺へ移動し、同様に3~5の流れを行う。船行神社へ戻り、神社用の祝いうたを唄ったのち、公民館、本要寺も同様に祝いうたを唄う。午後6時30分、各班に分かれて門周りを行った。
・門回りは以下の流れで行われる。1戸20分程度
1.家を訪ね、祝い申そうをしてよいかの確認をする。 23人のうち、1人はバチバチノキを持って台所へ、1人は豆をもっ て奥の間へ上り、一人は玄関先で待つ。
2.合図とともにバチバチノキを持った人はコンロで焼きながら「鬼は外」と大声で叫び豆を一つ投げる。玄関の人も「鬼は外」と叫びながら石を一つ外へ投げる。
3.次に奥の間の人が「福は内」と叫びながら豆を1個投げる。
4.「鬼は外」→「福は内」→「鬼は外」→「福は内」→「鬼は外」と 5回交互に行う。
5.最後の「鬼は外」の「外」は「そとーーー」と伸ばして叫びなが ら、それぞれ家の壁、戸、玄関をドンドン6秒ほど掌で叩く。
6.家主が「ありがとうございます」と頭を下げる。
7.3人で家へ上がる。
8.酒、ビール、つまみが準備され、飲みながら世間話等をする。
9.15分程話をした後に礼を言い、祝いうたの中に入れる名前、○○ ぶりの確認をする。
10.3人で玄関先に立ち、祝いうたを大声で唄う。最後の「申す」は 「もーーーす」と伸ばし、礼をする。
11.家主からご祝儀袋に入った祝儀(千円程度)を頂く。
・午後10時、すべて回り終えて解散となった。
【参考文献】屋久町郷土誌 第三巻集落誌 下
写真
船行門回り
午後6時、船行神社拝殿に集まる。 |
本殿に灯を灯す
本殿に3つ祀られている中で、真ん中のみ火を灯す。 |
門回りの前の礼
お参りを行う。 |
門回り前の直会
直会。お神酒を一口づつ口にする。 |
豆の準備
撒く為の豆を袋に入れる。 |
祝いうた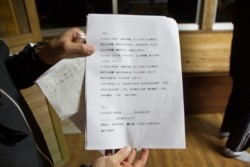
門周りで行われる祝いうた。 |
神社で戸や玄関を叩く
「そとーーー」のタイミングで戸、壁、玄関を掌でバン バン叩く。 |
公民館にて
公民館での「そとーーー」のようす。 |
公民館での祝い申そう
公民館でのようす。豆まき後、玄関前で祝いうたを唄う。 |
門回り
個人宅の門まわり。家々では門周りが来るのを待っている。 |
豆変わりの小石3つ
家々で準備されている、外で撒く豆変わりの小石3つ。 |
バチバチノキを炙る
台所にあがって、コンロでバチバチノキを炙る。 |
振る舞いのようす
豆まきのあとに各戸でお酒や一品が振舞われる1 |
振る舞いの様子
豆まきのあとに各戸でお酒や一品が振舞われる2 |
祝い申そう
祝い申そうのようす。全員で玄関前に立って唄う。 |