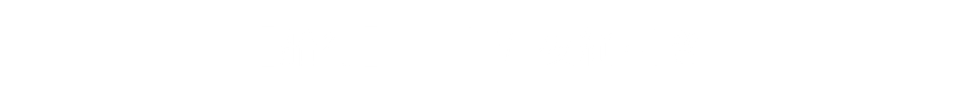十五夜綱引き
概要
【概要】
・旧暦8月15日に毎年行われ、少なくとも100年以上昔から行わ れている、農作物の豊作を祈願する伝統行事である。しかし、旧暦でいくと平日となる事もあるため、現在は旧暦8月15日前後の日曜に行われる事が多い。
・青年団がカヤを取ってくるのが通例だが、一時期は青年団の人手不足から各戸がカヤを一束づつ出していたようである。現在は青年団が取ってきている。
・今は神社の境内にて綱引きを行うが、昭和63年までは集落人数も多かった事等から本通り(町道)を使って行っていた。長さも50m以上あったという。
<綱(つな)の準備>
(平成29年10月1日実施)
・朝8時、船行神社境内に集まり、刈ったカヤの運搬、綱打ち用の台の組み立て、カヤの整えを分担し協力して行う。
・9時、台の組み立ても終わり、青年団が声を合わせながら綱を作っていく。
・縄は、縄を編む係、縄を引く係、カヤの束を差し入れる係、差し入れる為のカヤの束を整える係の協同作業で行われる。
・縄を編む係は3人一組となり、カヤの一束を捩じりながら3本を寄り合わせていく。そこへカヤの束を差し入れる係がタイミングよく入 れていくので、それぞれの呼吸合わせが大切となる。
・縄は短いものを1本(芯)、長いものを2本の計3本作る。
・船行では綱はカヤを編んだものだけで作る。他の集落では芯にロープを用いるところもある。
・1本の太さは10cm程度。3本組み合わせて1本になると20センチ程度の太さ。
・3本を寄り合わせる時も、綱を作る時同様に捩じりながら寄り合わせていく。
・11時20分頃に完成した。作業時間は3時間30分程度であっ た。
・出来上がった綱は、集めたカヤの上に置き、上からブルーシートを被せて十五夜当日まで置いておく。
<十五夜>
(平成29年10月4日実施)
・午後7時、月が出ると船行神社の階段に綱をトグロ状に巻き、中心に芋焼酎(お神酒)を置いて奉納する。
・お祈り後、綱にお神酒をかけ、参列者が一口づつお神酒を頂く。
・子供たちが綱の先頭を持って、綱を境内の中へ引っ張る。
・綱引きは引く前に必ず「十五夜のお月様 まーるやけて 子どものおかげで綱を引く」の口上を唄ってから引く。
・綱引きは船行区内を更に分けた上町と下町で分かれたり、年齢順に分かれたりしながら計10本ほどの勝負を行う。勝った方にご褒美や 負けた方に罰といったものは一切無い。
・綱引きがあらかた終わると、地面にカヤを敷き、その上に綱を直径3m程度に丸く囲って即席の土俵を作る。
・子供同士、トーナメント形式で草相撲をとる。参加した子供にはお菓子等が渡される。
・子供同士が終わると、大人同士や子供5人対大人一人といった番外 編の取り組みが行われる。
・午後7時半過ぎに十五夜は終了。終始笑顔の絶えない和気あいあいとした行事であった。
【参考文献】
屋久町郷土誌 第三巻集落誌 下
区長他、区民の聞き取り
写真
船行十五夜綱引き
十五夜綱引きのようす。 |
十五夜綱作り
鋼管を組み立てて綱打ち用の台を作る。 |
十五夜綱作り
縄作りのようす。作業を分担して行われる。1 |
十五夜綱作り
縄作りのようす。作業を分担して行われる。2 |
十五夜綱作り
3人で力を合わせて縄を編む。 |
十五夜綱作り
カヤを差し込んでいるところ。 |
十五夜綱作り
出来上がった3本の縄。短いものが芯となる。 |
十五夜綱作り
3本を編んで1本の綱にしていくようす。 |
十五夜綱奉納
船行神社に出来上がった綱を奉納する。 |
十五夜綱奉納
奉納時、酒をかける。 |
十五夜綱引準備
子供が先を持って綱を伸ばす。 |
十五夜綱引き
子供が中心となって一生懸命力いっぱい綱を引く。 |
十五夜相撲
カヤの上で子ども相撲1 |
十五夜相撲
カヤの上で子ども相撲2 |
十五夜相撲
大相撲の地方巡業のような複数の子供対大人の取り組みも。 |
十五夜相撲
相撲で盛り上がる。 |