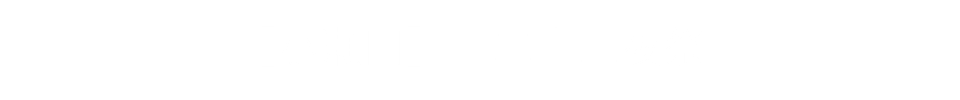二十三夜祭
概要
・旧暦1月23日に行われる民間信仰の行事で、かつては全国的に行われていた。二十三夜に昇ってくる月と太陽に集落の災厄払いの 願いごとをする祭りで、昔は島全体で行われていた大事な行事である。二十三夜マチ、月待ちとも言う。区の祭礼係が担当する。小瀬田は昔、民家で行っていたが、現在は公民館で行う。また、昔は新 築の民家でも家運隆盛を祈って行われたり、第二次世界大戦中は出征兵士の武運長久を祈願して行われた。昔は久本寺の住職にも読経をお願いしていたが、現在は行われていない。
<二十三夜祭>(平成31年2月27日実施)
・8:00頃から公民館につわぶき会(小瀬田区婦人会)が集まり、お供え物や食事の準備を始める。公民館建物の角々に竹を立てる。
・18:00 小瀬田神社へ祭礼係が参拝を行う。今回は祭礼係の都合が悪かったので、区長と役員が務めた。神社下の海岸でツワブキの葉と海水で清められた小石を拾う。
・公民館ではお供え物が準備されており、ロウソクに火を灯し、線香をたてて集落の繁栄を祈願する。拝礼は仏式(法華宗)。
・18:30 公民館に区の役員も集まり、二十三夜祭が始まる。お吸い物を飲み、食事をしながら酒を飲み、月の出を待つ。
・お供え物の品は「酒」、「サカキ」、「ロウソク」、「線香」、 「海岸の小石」、「里芋(調理加工されていない葉付のもの)」、五穀(「米」「小豆」「大豆」「麦(押麦)」「キビ」)、「塩」、 「赤飯(重箱の中 ) 」、「カメノテ」、「トコロ(オニドコロの 根)」、「紅白餅(それぞれ大(丸形)1個、大(三日月形)1個、中12個、小365個)」。神仏混合の内容である。
・この日の月の出は2:11だったが、平日という事もあり0:00に月に向かって礼拝する。礼拝後、お吸い物を飲む。祭礼係以外は帰宅し、祭礼係は公民館で泊まる。帰る前には赤飯を一口貰ってから帰る。
・翌日朝6:00過ぎ、祭礼係は小瀬田神社へ再度参拝する。その 後公民館に戻り、日の出となる6:45、日の出に向かって礼拝する。礼拝後、そうめん入りのお吸い物を飲んで行事は終わりとなった。
【参考文献】
1上屋久町郷土史/上屋久町
2小瀬田の伝統行事伝説方言録/小瀬田愛郷会
3区長他、住民の聞き取り
写真
二十三夜祭
二十三夜祭のお供え物。 |
料理する婦人会
婦人会が料理を作る。 |
紅白餅を作る
紅白の餅を手作りで作る。 |
竹を立てる
公民館建物の角々に立てられた竹。 |
神社下で石を拾う
小瀬田神社下の海岸で石を拾う。 |
神社で参拝する
小瀬田神社にて参拝。 |
お供え物
二十三夜祭のお供え物(全体)。 |
五穀のお供え物
二十三夜祭のお供え物(五穀)。 |
三日月形の餅
二十三夜祭のお供え物(餅)。 |
礼拝
集落の安全と繁栄を願う。 |
参加する役員
役員が集まり、宴が始まる。 |
季節の郷土料理
季節の郷土料理が並ぶ。 |
酒を飲んで過ごす
酒を飲みながら時間を過ごす。 |
月の出の礼拝
月の出に合わせて東の方向へ向かって礼拝する。 |
締めのお吸い物
締めに出されるお吸い物。 |
お吸い物を頂く
お吸い物を飲む。 |
赤飯を一口
赤飯を一口ずつ食べる。 |
全員で参拝
日の出に合わせて東へ向かって礼拝する。 |
集落を望む
締めに出されるそうめん入りのお吸い物。 |
マチムケ
お吸い物を飲んで終わる。 |