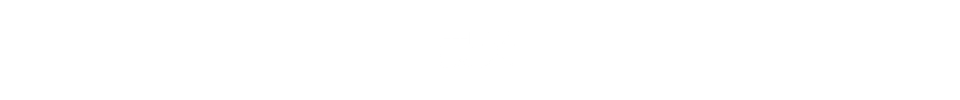環境整備
概要
<稲作>
・1922(明治44)年完成の17h(耕地整理記念碑では18h)の開田 によって、それまで切替え畑形態であった麦生の農業が水稲作を基本
に本格化した。
・開田の事跡を記した耕地整理記念碑が1929(昭和2)年に建てられ、田の神水神様や平成になって行われた畑総整備事業の碑ととも に水田地帯を見下ろす森山の一角に並んでいる。
・110年を経た今も、麦生農業のシンボルとして前岳を背に特徴ある農村景観をなしている。
・台風や病虫害を避けて3月に田植え、梅雨明け稲刈りの早期水稲栽培が行われている。
・伝統ある田んぼを生かし、他地区に先駆けて緑肥と景観づくりのルーピンやコスモスが花を咲かせている。
<ポンカン、タンカン>
・大正時代に台湾から導入されたポンカンは、長年栽培されてきた。
・昭和4 0年代の製糖工場閉鎖に伴うサトウキビ生産の減少と、商品作への関心の高まりを背景に、ポンカン栽培が盛んになった。
・さらにタンカンの導入と優良品種の開発があってポンカン、タンカン生産が農業の中心になっている。
・近年はオレンジ風味のタンカンの人気が高く、ポンカンをしのぐ生産量になっている。
・平成の畑地灌漑事業で鯛之川の水が樹園地のスプリンクラーに供給されるようになり、生産が一段と安定した。
<さまざまな畑作>
・昭和40年代の製糖工場閉鎖は、サトウキビやカライモ生産から市場性の高い輸送野菜へと畑作を大きく転換させるきっかけになった。
・水田裏作の実エンドウと早掘りバレイショが奨励され、一時は盛んに栽培された。
・恵命我神散の原料である薬草ガジュツに加え、最近は近縁のウコンも栽培されている。
<花卉園芸>
・施設栽培のドラセナなど葉物やシンビジュウムの切り花が産地化している。
【文献・資料】
屋久町郷土誌第二巻村落誌中
広報むぎお
区長他聞き取り
写真
麦生田んぼ田植
まとまって広がる麦生田んぼの田植 |
農業関連碑
開田記念碑他農業関連の碑が水田を見下ろして建っている |
3月の田植
早期水稲の田植は3月 |
7月の稲刈り
台風と虫害を避けて7月に稲刈り |
稲刈り海バック
海を目の前に稲刈り |
稲刈りコンバイン
今はコンバインによる稲刈り |
ポンカン
山を背に実るポンカン |
ポンカン収穫
ポンカン収穫作業 |
ポンカン収穫UP
ポンカン収穫作業1人 |
ポンカン選別
倉庫でポンカン選別 |
タンカン
色づいたタンカン |
タンカン収穫
タンカン収穫 |
タンカン収穫キャリ
タンカン収穫キャリも |
実エンドウ
一時より少なくなったが、栽培される実エンドウ |
春ウコン
ガジュツの仲間薬草春ウコン |
春ウコン追肥
春ウコンの施肥作業追肥 |
ドラセナ施設
葉物出荷するドラセナの施設 |
ドラセナ選別
市場出荷のドラセナ選別 |